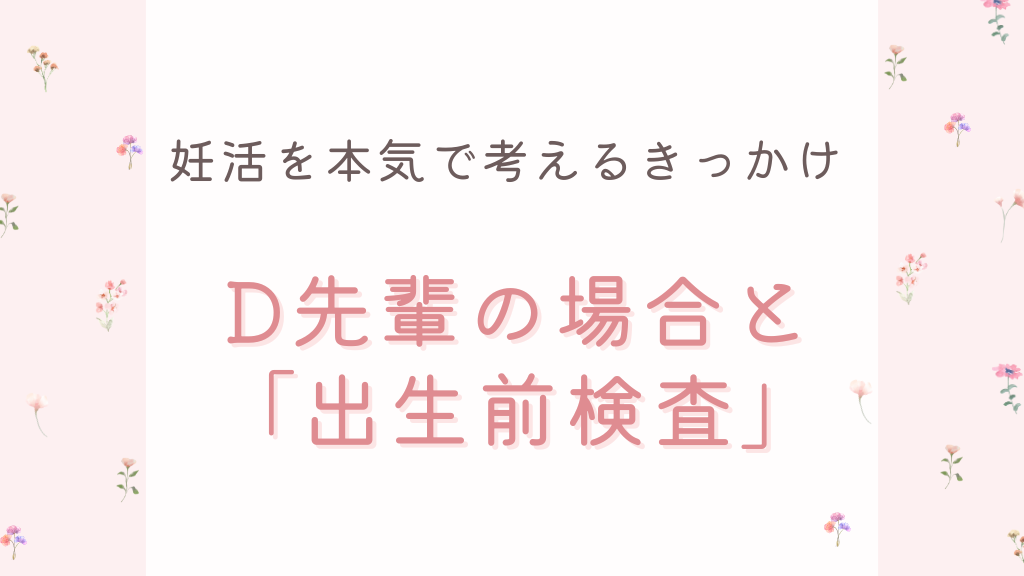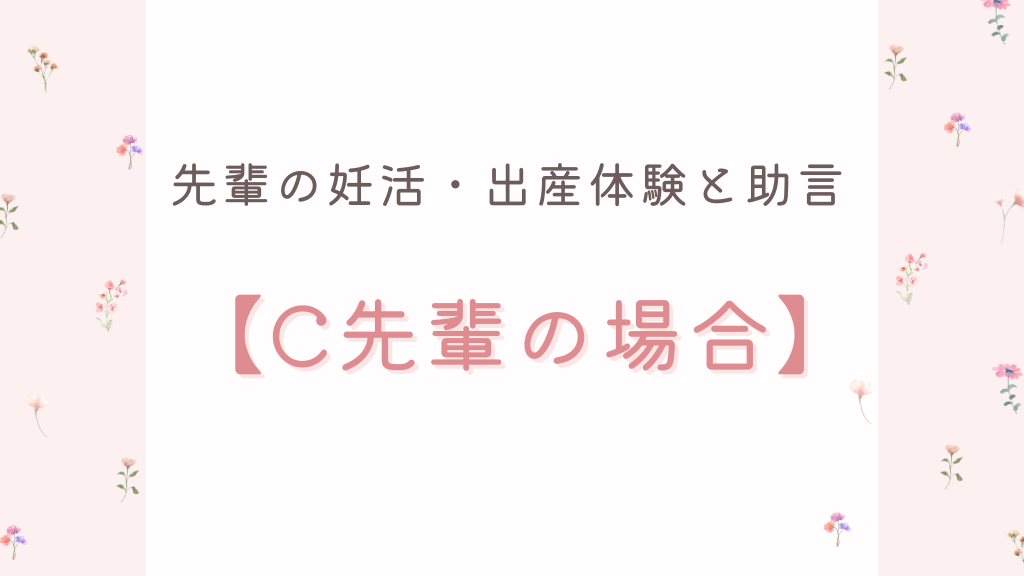これまで3人の先輩の妊活や出産について話を聞いてきたが、最終的に私が妊活を真剣に考える決定打となったのが、D先輩の話だった。
D先輩とは部署もフロアも違っていたが、あるきっかけから会話をするようになり、すぐに打ち解けた。
まるでディズニープリンセスのような小顔にパッチリした目、華奢な体型で、誰もが憧れる存在。
それでいて気取らず、明るくサバサバとした性格が魅力的で、同性の私でも好きにならずにはいられなかった。
そんなD先輩にはすでに小学生の娘さんがいたが、もう一人子どもが欲しいと、40歳で妊活を開始。1年ほど経って妊活を諦めたタイミングで、自然妊娠したという。
妊娠5ヶ月の頃、仲良しメンバーでランチ会をしたときのこと。誰かが「高齢出産になるし、染色体検査はした?」と尋ねた。
先輩は、「どんな子でも産むって決めてるから、検査はしてないんだ〜」と、明るく答えていた。
検査を「しない選択」と「する意味」
個人的に、検査の話が出るとすぐに「産む or 産まない」の選択に直結させようとする人が多いことに、少しモヤモヤする。
染色体検査やその他の出生前診断は、「産むかどうかを決めるため」だけのものではない。
私は、検査のもう一つの大切な役割 ”事前に準備を整えること” にも注目してほしいと思っている。
たとえば、障害や疾患があると分かっても「産む」と決めているならなおさら、出産後すぐに対応できるように、心の準備と情報収集が必要だ。
・出産直後に事実を受け入れられるか?
・対応に必要な知識・物品・医療はどんなものか?
・サポート制度や福祉の準備は?
これらを産後に急いで対応するのは、キャパオーバーの原因になりやすく、産後うつのリスクも高まる可能性がある。
私は「検査=中絶を選ぶための判断材料」ではなく、「準備をするための情報」と捉えている。
D先輩が語ってくれた出産後の現実
話をD先輩に戻そう。
出産後、産休中に子どもを見せてもらう約束をしていたが、音沙汰がないまま数ヶ月が過ぎた。
連絡を取ってもなかなか予定が合わず、生後10ヶ月を過ぎた頃、ようやくランチで会えることに。
しかし、赤ちゃんを連れてくる予定が「母に預けてきた」とのこと。
少し残念に思いながらも、久しぶりの再会に話が弾んだ。昔話や育休中に起きた社内のトラブル、大きな人事異動などで盛り上がった。
その日の終わり、D先輩が静かに語った。
「うちの子、ダウンちゃんだったの」
その瞬間、場の空気が変わった。
先輩は笑顔だったが、その笑顔の裏にある時間と葛藤が、にじみ出ていた。
出産直後、看護師の「染色体検査」という言葉や慌ただしい空気で察したという。
分娩台で過呼吸になり、その後半年間は涙が止まらず、誰にも話せないほど心が不安定になったそうだ。
ようやく今、少しずつ前向きに受け入れられるようになったと話していた。
あんなに強く見えたD先輩でも、こんなにつらい経験をしたのかと思うと、胸が苦しくなった。
D先輩は最後にこう言った。
「年齢に余裕があるうちに産みなさい。年を重ねるほどリスクは増えるよ」
この言葉には圧倒的な説得力があった。
帰宅後、私は【妊娠 確率】、【染色体異常 年齢別 確率】などを検索し始めた。
知らないワードが出てくるたびに調べ、気づけば朝4時。
「35歳くらいで産めばいいかな〜」なんて思っていた過去の自分を、叱ってやりたくなった。
この日を境に、私は本格的に夫と妊活について話し合おうと決めた。